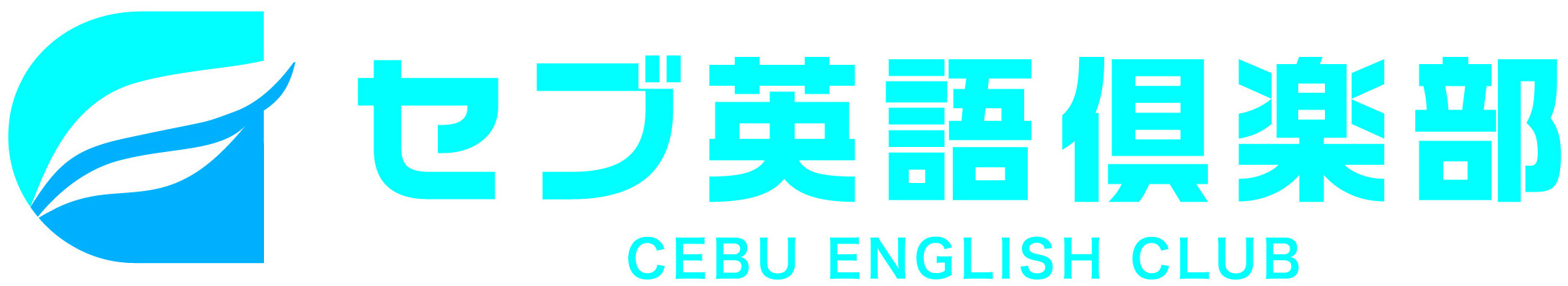日本人にとって英語が“遠い”理由と、勝ち筋の学び方(言語間距離を踏まえて考える)
まず最初に、元記事はこちらです。内容の骨格を共有しつつ、今回は新しいエビデンスと実践へ落とす視点を加えて再構成しました。
【言語間距離という概念】英語が日本人にとって特別難しい言語である理由
結論から言います。英語と日本語は遠い。だから、苦戦は正常です。ここを直視しないと、学習計画は最初から齟齬だらけになります。
“The limits of my language mean the limits of my world.” — Ludwig Wittgenstein
「私の言語の限界は、私の世界の限界である。」
言語間距離とは何か
言語間距離(linguistic distance)は、二つの言語の「構造的な遠さ・近さ」を指す考え方です。語順、音声体系、語彙、形態論など、複数の次元から総合的に測ります。感覚論ではありません。定量と構造で見ます。
新しいエビデンスで見る「英語と日本語の遠さ」
1)学習時間のハード指標:FSI分類
米・外交官養成機関FSIの指標では、英語母語話者が日本語を業務レベルにするには約88週間(≒2,200時間)の集中的訓練が必要とされます。最難度群のひとつです。方向は「英語→日本語」ですが、両言語の距離が大きいことを端的に示す指標です。
2)語順と統語タイプ:SOV vs. SVO
日本語はSOV(主語–目的語–動詞)。英語はSVO(主語–動詞–目的語)。さらに日本語はヘッド最終の性質が強く、英語はヘッド初期。文を処理する際の「脳内手順」が根本から違います。逐語訳がすぐ破綻するのはこのためです。
3)冠詞という概念:ある言語・ない言語
英語には定冠詞 theがあります。日本語には冠詞がありません。情報の「既出・共有」や「特定化」を冠詞で明示する英語と、文脈や指示表現で補う日本語。理解の入口がそもそも異なります。
4)母音インベントリの差:音の“粒度”が違う
日本語の母音は概して5音。英語は方言差も含めて有意に多い(7〜14程度)。つまり聞き分けと発音で、英語は微細な対立が多い。/ɪ/と/iː/、/æ/と/ʌ/など、最小対立が初学者のハードルになります。
5)語彙の縁続き:ヨーロッパ語同士は“近い”
ロマンス語間では語彙の類似度が高い組み合わせが多く見られます。たとえばスペイン語×ポルトガル語、イタリア語×フランス語など。系統的に近いがゆえに、相互学習の摩擦が小さい。日本語×英語は系統も構造も遠いため、この“追い風”がありません。
ここからは“覚悟と反復”
細かい理屈は一旦置きましょう。
違いを知ったら、腹をくくる。
まずは暗記。暗記なら誰でもできます。
最初は遅い。覚えられない。
それで正常です。
けれど学習は加速する。反復で処理速度は上がるのです(power law of practice)。
量をこなせば、質は後から追いつく。これは経験則ではありません。帰納的に妥当です。
“Repetitio est mater studiorum.”
「反復は学習の母である。」
だから、開き直りましょう!
自分に言い訳しない。淡々と積む。機械的でいい。機械性は習熟の味方です。
そして忘れるないでください。
スペイン人が英語とイタリア語も話せるのとは訳が違うのです。
日本語と英語は段違いに難しい。だからこそ、方法論コレクターになるのはやめましょう。
メソッド談義は後回し。
やる。
今日やる。
Let’s do it.です。
まとめ(KGの一言)
- 英語と日本語は、構造・音・語彙の三拍子で“遠い”。
- 遠いなら、覚悟して反復する。最初は遅くていい。必ず速くなる。
- 量が質を呼ぶ。今日は1ページ。明日は2ページ。淡々と。
悩んでいるなら、今日から“距離”に合わせた練習を始めよう。僕が背中を押します。
参考・出典
- FSI Language Difficulty(日本語は最難度群・約2,200時間)
- WALS: Order of Subject, Object and Verb(日本語SOV、英語SVO)
- WALS: Definite Articles(英語は定冠詞あり、日本語は冠詞なし)
- WALS: Vowel Quality Inventories(英語=大型、日本語=平均的)
- Lexical similarity among Romance languages(ロマンス語間の高い語彙類似度)